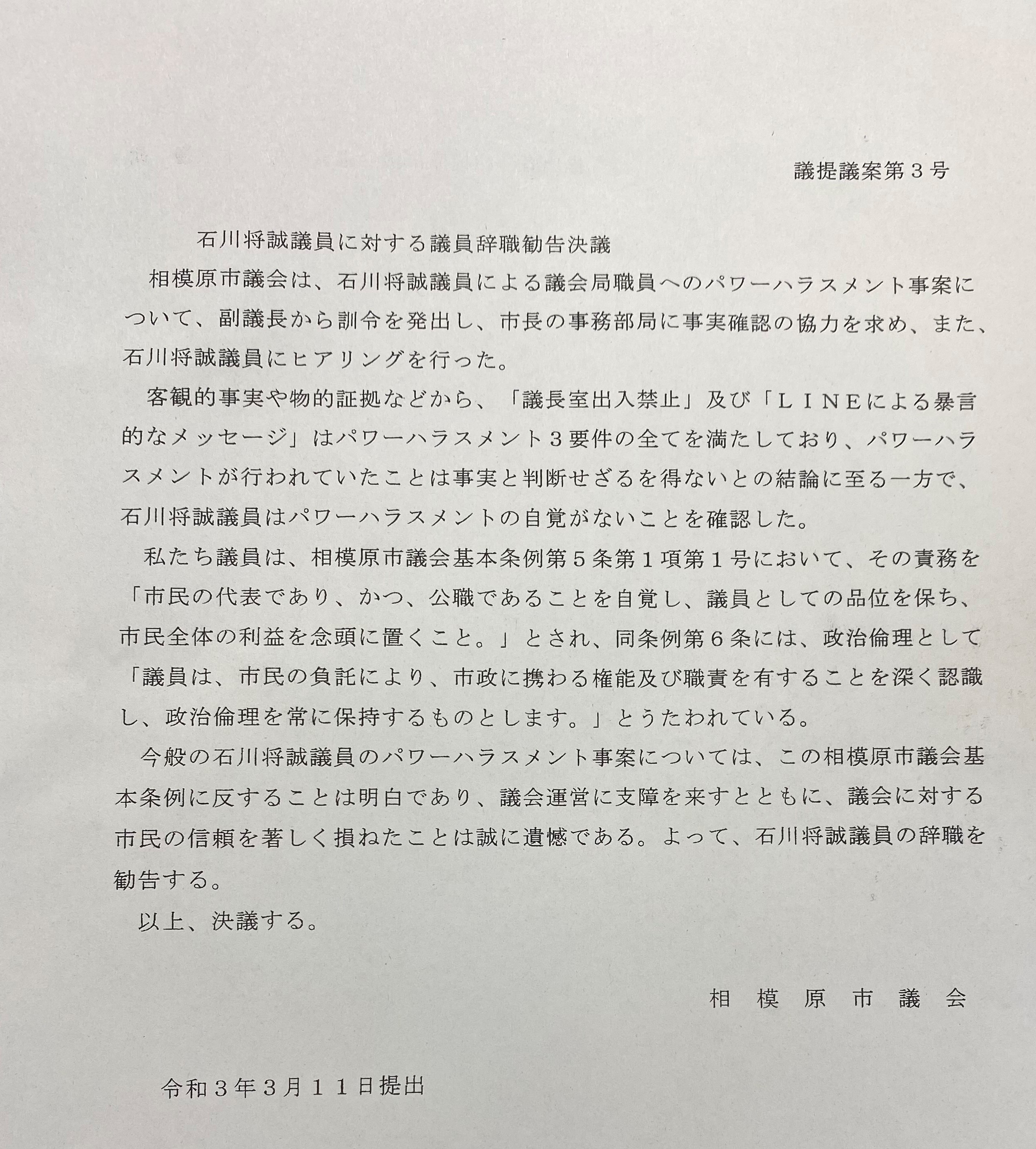2日間の代表質問が終わりました。自民・民主、2会派の1問目は55分~56分と1問目で1時間です。コロナ禍の議会運営では、1時間に一度20分程度の休憩をとる、とされているため、公明さんはそこまでではないですが、やはり3会派の代表質問の項目と1問目の時間はかなりです。
2日間の代表質問が終わりました。自民・民主、2会派の1問目は55分~56分と1問目で1時間です。コロナ禍の議会運営では、1時間に一度20分程度の休憩をとる、とされているため、公明さんはそこまでではないですが、やはり3会派の代表質問の項目と1問目の時間はかなりです。
24日は先行する2020年度の補正予算の採決もあり、質問者は2人で6時過ぎまでかかることになりました。
24日の補正予算は、主なものは、私立幼稚園などに対するコロナの対策費用を1園あたり50万円、国が100%交付する、コロナ感染症緊急包括支援交付金といういわゆる”特定財源”です。220園分で1億1,000万円です。国から県に行き、県から市に交付されます。
ところが、この補正予算が提案された2月15日時点で、私立幼稚園の中の14園=700万円分は、交付金の対象外になるとわかっていたというのです。「幼保連携」がいわれ、進められてきましたが、幼稚園の中で、一時預かりや園長保育を実施している園は対象になるものの、新制度に移行していない幼稚園14園は対象外とされるということで、つまり文部科学省と厚労省の縦割りの弊害は解消されていないのです。
一時預かりなどの保育は厚労省です。厚労省としてこの対象外になる園には出さない、ということなのでしょうか。ただ、そのことを市の担当課は、私立幼稚園の問い合わせから確認をし、15日の前にわかっていたのに、15日には、700万円は”執行残”として残すことを前提にしつつ、そのことを議会には説明せずに、全額執行されるかのように提案したのです。
私達の会派「颯爽の会=さっそうのかい」は3人で、この議案が審査される民生委員会に委員を出していません。委員会の議案の審査が18日でした。15日の提案後に委員のいる会派には説明されたそうですが、颯爽の会には、委員会の前日17日に会派の代表に説明があったのです。
この件を共有した私達の会派として、これはやはり議会に対し、議案提案の在り方として誤っている、と結論を出し、本来なら、議運で前もって提案があり、財源の手当てをどうするかなどがあって異例の案件として説明付きで正されるべきもの、としました。
18日の民生委員会の日は私は自分の建設委員会の補正がありましたが、会派の控室では傍聴されていて、公明の議員だけはこの点を委員会で質したことはわかりました。
その上で、議案は賛成総員で採択はされたということで、私達はどうしようか、と議論し、討論しておくべき、として会派では討論して賛成としました。公明さんも討論したので、複数の会派が討論したことは良かったと思っています。どうも最近の議案の提案の在り方には、首をかしげることがあるのです。
議事課にこの点を質すと、議事課も民生委員会の質疑まで知らなかった、と。おかしなことが起きています。
さて、25日の私の代表質問です。項目は、①東日本大震災から継続している放射性物質の検査・測定のこと。②予算編成の考え方 ③予算編成と「行財政構造改革プラン(案)」④コロナ対策に乗じた公共施設の閉鎖のことや生活保護の扶養照会の実際など ⑤コロナ禍で増える精神保健福祉相談の各区ごとの件数と職員一人当たりの件数 ⑥市が昨年末策定した「社会的養育推進の基本的方向性」について、児童相談所の一時保護と施設のひっ迫した状況と必要な施設などのこと ⑦伊勢丹跡地の「相模大野4丁目計画(仮称)」建設計画で公共歩廊の確保策とまちづくりの提案 ⑦議案第14号みんなのシビックプライド条例(案)について、です。
30分の質疑時間と3回の質問回数で、これらをどこまでやれるか、本当に厳しくて、いつもながら、言えなかったこと、もっと言いたかったことがある、などはたくさんあります。「行財政構造改革プラン(案)」(以下プラン)があまりにコストカット優先で、これまでの行財政運営を続けたら将来的に真に必要な行政サービスの提供すらできなくなる、という脅しのような文言とともに、議会の全員協議会と市民のパブコメにかけられたため、これをやらないわけにもいきません。
このプランに、「廃止」ありきのような公共施設やサービスが盛り込まれたことで、当たり前ですが、市民は個別の施設がなくなることへの反対意見や危惧を持ちます。それらで、市民のパブコメには、1300人の意見が寄せられたと、代表質問でも答弁されています。
私はプランで一番問われるべきは、「構造改革」なき構造改革というプランの策定過程と考え方そのものと思っています。
で、これまでの行政運営とは、どういう手法をいうのか、市民に真に必要なサービスを提供できなくなる事態、というならそうなった要因と責任を詳細に分析、評価を明らかにすべきと、と質し、議論したかったのですが、そうはできなかったのが悔やまれます。
前市政の4~5年前に私たちは、財政の中長期の見通しと10本を数えた大規模事業の財源確保の見通しなどを併せて示すように幾度も求めた経緯があります。しかし、当時は真っ黒塗りで出てきたこと、そして結局、いやいやのようにJR横浜線の立体交差化や地下化などの事業は当座棚上げする、としたことなど、前市長のもとでの放漫経営に責任はあり、前市長を忖度するように支えた今の副市長など一部幹部にも当然説明責任があると考えます。
財源の裏付け無き大規模事業の一つに、上の写真の麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業もあると思います。この事業ストップは、偶発的なものではなかったのでは、と前市政について考えざるを得ないところです。
しかし、なぜ前市政の4年前に中長期の見通しを出せなかったのか、などの問に、隠田副市長は、総合計画の実施計画で特財など財源がついた時にやれるものをやる、としてきて長期見通しを立てることまでは希薄だった、ような他人事のような答弁のみです。
そういう場当たり的な役所の在り方が変わるのか?という問いには答えませんでした。構造改革なきコストカットプランで、どんな将来像を描くのか、も明らかにせずに痛みだけを押し付けるように、扶助費(子ども子育てや福祉にかかわる費用)を悪者にし、公共施設ごとで市民を分断するように一方的に方針を出すのは、市としての責任も果たせませんし、今のコロナ禍で疲弊する市民に対しやってはいけないことを一番にやるようなものです。
2010年に政令市に移行した際、県から移譲された事務の大きなものは、児童相談所と精神保健福祉分野です。他に国県道の維持管理などもありますし、市でもっていなかった診療所の運営などもあります。でもなんと言っても児童相談所は大きいことです。
それまで福祉専門職の計画的な育成をやってこなかった市にとって人材育成の課題は、ずっと改善されず今も途上と思っています。都市部を抱える市では、一時保護も長期化し、高齢児童(中学生以上で18歳前後の子どもも)も増え、その背景にはコロナ禍でのストレスや不安定を抱えて経済格差が広がっている大人社会の実情があります。
でも市には、「児童心理治療施設」も「児童自立支援施設」もないのです。県や川崎市などの空いている部分を利用させてもらう、「割愛」という話あいでしのいできています。こどもの虐待通報件数や、一時保護される子どもの中に、より支援の難しい子どもが増えて、長期化したり、受け入れる児童養護施設がなかったりしている中では、こうした施設を自前で確保することがどうしても必要と思うのです。
精神保健福祉相談も、都市部の南区は中央区の2倍以上にもなっている現状は、政令市の仕事の大変さ=現場でコロナに疲弊する市民に向き合う職員の大変さも表しています。
この2つの責任業務に対し、自転車操業のようにやってきた政令市移行10年のツケがコロナで表面化しているのではないか、と思えるのです。国が社会保障費を削減しようと、公立の病院を独法化してきたことや、県が保健所などの出先機関を絞ってきてしまったことが、コロナで脆弱性として表れてきたこととも重なるように思えます。
相模原市が政令市の責任としての移譲事務について、計画的に人材と施設整備を進めてこなかったことと、中長期的財政収支見通しを市民や議会に示し共有化しながら、市としての将来像と方向性をつくる努力をしてこなかった、ということは裏表です。
誤りを正し、明らかにし、市の将来像を一部の財政担当の職員でつくるのではなく、市民や議会も、現場の職員も含めてまずは丁寧な議論を重ねてつくっていくのが構造改革の基本になるのではないか、と言いたいのです。
放射能測定では、給食食材は、絞って測定を月に一度継続していくことや、最終処分場の埋めたて場所の地表線量測定もやっていくことで監視体制も続けると答弁しました。本当は焼却灰も継続してほしいのですが、この点はまた担当には話をしていきます。
そして、精神保健福祉の相談についての担当は事務職と入れ替えると言いますが、実際に職員数は増やさないのか、そこもチェックが必要です。生活保護の扶養照会は、全てなくすとは言わないのですが、より弾力的には運用すると言っていますし、また件数のチェックをしていくつもりです。
みんなのシビックプライド条例案については、これもかみ合わないままです。シビックプライドをなくすようなプランや、コストカット優先の魅力の見えない予算編成で、どうやって市民が街に愛着を持てるのか、、。施策の結果で市民は住みたいまちを決めるのだと思います。
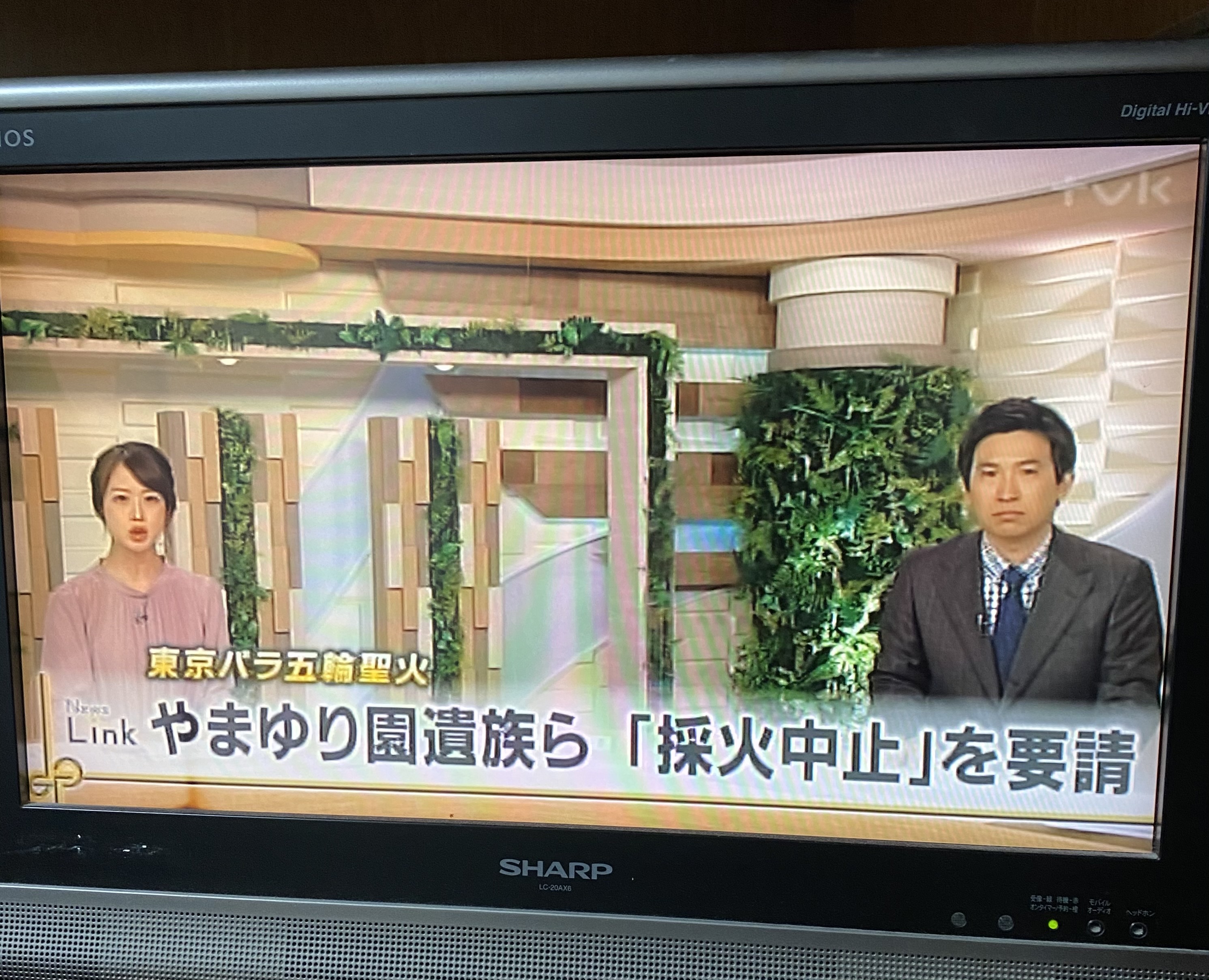 津久井やまゆり園でオリンピックの採火を、という話を知ったのは、3月23日のNHKのニュースをSNSで見てのことです。
津久井やまゆり園でオリンピックの採火を、という話を知ったのは、3月23日のNHKのニュースをSNSで見てのことです。